はじめに
現在東京国立博物館で開催中の特別展『挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」』に行ってきました!今回は、その魅力を皆さんにお伝えしたいと思います。
平成館 特別展示室
2024年10月16日(水) ~ 2024年12月8日(日)

そもそも埴輪とは?
埴輪は今から約1750年前、古墳時代に始まった日本独自の文化遺産です。古墳の周りに立て並べられたこれらの素焼きの造形は、当時の人々の暮らしや文化を現代に伝える貴重な”タイムカプセル”としての役割を果たしています。
展示の見どころ
1. 「埴輪 踊る人々」の復活
東京国立博物館が誇る名品「埴輪 踊る人々」が、約1年半の修理を経て初お披露目されています。クラウドファンディングによって支えられた修理プロジェクトの成果を、じっくりと観察することができます。
2. 王たちの物語
古墳時代を通じて、埴輪は権力者たちの変遷とともに姿を変えていきました。
- 前期(3~4世紀):宝器を持つ司祭者としての王
- 中期(5世紀):武具に身を固めた武人としての王
- 後期(6世紀):金色に輝く馬具や装飾付大刀を持つ官僚としての王
それぞれの時代を代表する国宝級の副葬品とともに、王たちの姿を見ることができます。
3. 史上初!5体の挂甲の武人が集結
展示の目玉は、なんといっても国宝「埴輪 挂甲の武人」とその兄弟たち。通常はアメリカのシアトル美術館に所蔵されている1体を含む、5体の挂甲の武人が史上初めて一堂に会しています。最新の研究成果も含めて、その魅力を存分に味わうことができます。
4. 地域色豊かな埴輪たち
北は岩手県から南は鹿児島県まで、日本各地で作られた埴輪には、それぞれの地域性が色濃く反映されています。精巧な作りのものから、どこか愛らしい素朴な造形まで、バリエーション豊かな埴輪たちとの出会いが待っています。
5. 埴輪が語る物語
展示では、埴輪たちが演じる様々な”物語”を見ることができます。
- 古墳を守る盾持人(たてもちびと)
- 邪気を払う相撲の力士たち
- 王の居館を再現したとされる家形埴輪
- 生き生きと表現された動物たち etc…
さいごに
今回私は平日の昼間に行きましたが、そこまでの人混みではなく、ゆっくり鑑賞することができました!
約半世紀ぶりという貴重な機会に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?
(おまけ)
ハローキティ展は入場40分待ちですごい列でした…。

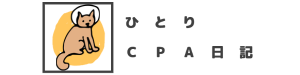

コメント